
退院後の生活に必要な介護用品を知ろう
退院を迎えることは一つの大きな節目ですが、その後の生活にはさまざまな準備が必要になります。特に、日常生活をスムーズに送るためには、適切な介護用品の準備が欠かせません。退院後は、ご本人の体調が安定していない場合も多く、無理なく生活できるようサポートするための道具が必要です。
介護用品の準備は、退院の1〜2週間前から始めるのが理想です。病院の医師や看護師、ケアマネジャーと相談しながら、必要な用品をリストアップしておくとスムーズです。また、介護保険制度を利用することで、必要な用品の一部を費用負担を抑えてレンタル・購入できる場合もあります。これをうまく活用することが、経済的な不安の軽減にもつながります。
この記事では、退院後の生活に必要な介護用品について紹介します。
CONTENTS
ここでは、退院後の生活において、多くの方が最初に必要となる基本的な介護用品をリストアップしてご紹介します。
寝起きや姿勢変換をサポートする介護ベッドは、床ずれ予防や介護者の負担軽減に役立ちます。高さ調整機能やリクライニング機能など、様々なタイプがあります。マットレスは、体圧分散性に優れたものを選ぶことで、床ずれのリスクを軽減できます。ベッド柵は、寝ている間の転落防止や、起き上がりの際の支えとして活用できます。
ご本人の移動能力に合わせて、車いす、歩行器、杖などの移動補助用品を検討しましょう。車いすは、長距離の移動や外出時に便利です。歩行器は、歩行時の安定性を高め、転倒のリスクを軽減します。杖は、軽度の補助で済む方に有効です。専門家と相談しながら、適切なものを選ぶことが大切です。
トイレまでの移動が困難な場合は、ポータブルトイレの設置を検討しましょう。設置場所やご本人の状態に合わせて、様々な種類があります。おむつ類は、ご本人の排泄状況に合わせて、適切なタイプとサイズを選ぶ必要があります。肌トラブルを防ぐために、通気性の良いものを選ぶことも重要です。
体を清潔に保つための清拭用品(体を拭くためのタオルやウェットシートなど)や、口腔ケア用品(歯ブラシ、歯磨き粉、マウスウォッシュなど)は、感染症予防や快適な生活を送る上で欠かせません。特に、口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防にもつながるため、しっかりと行いましょう。
基本的な介護用品に加えて、ご本人の症状や状態によっては、さらに特別な介護用品が必要になる場合があります。
片麻痺などがある場合は、食事や着替えをサポートする自助具や、リハビリテーションに用いる装具などを検討します。専門家のアドバイスを受けながら、ご本人が日常生活を送りやすくなるような補助具を選びましょう。
寝たきりの状態が続く場合や、皮膚が弱い方の場合は、褥瘡(床ずれ)を予防するための体圧分散マットレスやクッション、ポジショニングピローなどを検討します。定期的な体位変換と合わせて、適切な予防用品を使用することが重要です。
認知症の症状がある方には、徘徊防止のためのセンサーや、コミュニケーションを助けるための絵カード、生活リズムを整えるためのタイマーなど、認知症の進行や状態に合わせた介護用品が役立つことがあります。
食事をする際の姿勢を保つためのクッションや、握力の弱い方でも使いやすい自助食器、飲み込みが困難な場合の食事用具などを検討します。安全に食事を楽しめるように、工夫が必要です。
数多くの介護用品の中から、ご本人に合ったものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず最も重要なのは、ご本人の身体状況や症状を正確に把握することです。麻痺の有無、移動能力、排泄状況、認知機能などを考慮し、必要な機能を備えた介護用品を選びましょう。
介護用品を使用する場所の広さや形状、バリアフリーの状態などを確認し、住環境に合ったサイズや機能の製品を選びましょう。例えば、車いすを使用する場合は、廊下や出入り口の幅が十分であるかなどを確認する必要があります。
介護者がご本人の日常生活をサポートすることに大きな負担を抱える場合があります。移乗をサポートするリフトや、入浴を補助するバスボードなど、介護者の身体的な負担を軽減できる介護用品も積極的に検討しましょう。
介護用品の種類によって、費用は大きく異なります。レンタルできるものと購入する必要があるもの、介護保険が適用されるものとそうでないものなど、費用面についても事前にしっかりと確認し、予算に合わせて無理のない範囲で選びましょう。
介護用品は、様々な場所で購入・レンタルすることができます。費用についても、介護保険の適用などによって大きく変わる場合があります。
介護ベッドや車いすなど、使用期間が短期間での利用であったり、高価なものはレンタルがおすすめです。一方、使い捨ての衛生用品や、肌に直接触れるものは購入が一般的です。ご本人の状態や使用頻度、費用などを考慮して、レンタルと購入を使い分けましょう。
※車いすを例に挙げたレンタルと購入の違いの記事も掲載しています。是非こちらもご覧ください。
⇒『車いすの自費レンタルの料金は?購入との違いや種類と料金もご紹介』
介護保険を利用することで、一部の介護用品は自己負担額を抑えてレンタルまたは購入することができます。対象となる品目や条件、申請方法については、ケアマネージャーや地域の福祉用具貸与事業所に相談してみましょう。
介護用品の選び方や購入方法に迷った場合は、専門知識を持つ人に相談するのが安心です。福祉用具専門相談員がいる事業所や、地域の包括支援センターなどに相談してみましょう。実際に製品を見て触れることができる展示場などもあります。
介護用品の費用は、種類や機能によって大きく異なります。例えば、介護ベッドのレンタル費用は月額数千円から数万円程度、車いすのレンタル費用も同様です。購入する場合は、さらに高額になることもあります。事前に複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
退院後の生活を安心して送るためには、必要な介護用品を早めにリストアップし、優先順位をつけて準備することが大切です。ご本人の状態や住環境に合わせて、無理なく使える用品を選びましょう。介護保険制度を活用すれば、費用面の負担も軽減できます。困ったときは、地域包括支援センターや福祉用具専門相談員、ケアマネジャーなどの専門家に相談し、最適な用品選びや手続きをサポートしてもらいましょう。
介護用品の選び方や購入方法、費用の詳細については、信頼できる専門サイト「よぐGO」で詳しくご案内しています。初めての方でも分かりやすく、商品選びや相談も気軽にできますので、ぜひご活用ください。
退院後の介護用品選びやご相談は「よぐGO」へ!
あなたの安心した在宅生活をサポートします。
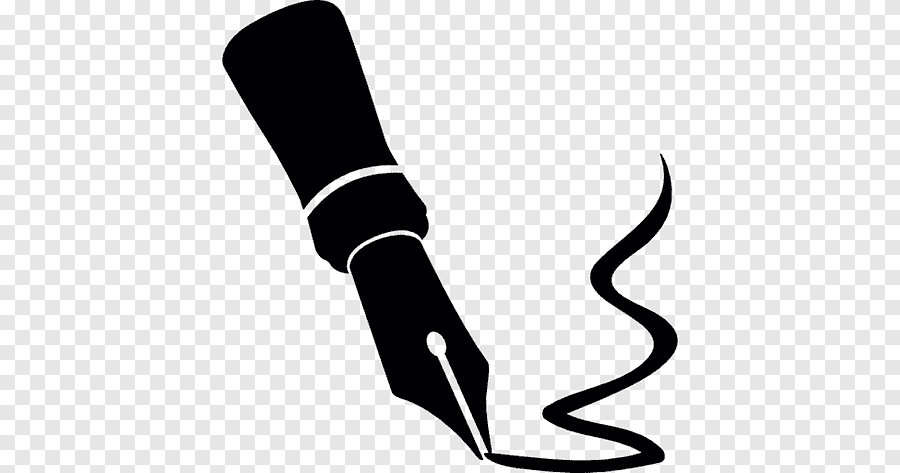 この記事の筆者
この記事の筆者
メールでのお問い合わせは下記にご記入、送信してください